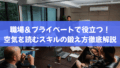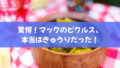「朝令暮改」と聞くと、何度も変わる命令や指示に対する不安感を抱く方も多いのではないでしょうか。
上司や社長がこのような姿勢を見せると、部下や社員は混乱し、信頼を失ってしまうこともあります。
しかし、一方でその柔軟性がビジネスにおいて重要な役割を果たすこともあります。
本記事では、「朝令暮改な上司・社長」がリーダーとしてどのように影響を与えるのか、メリットとデメリットを徹底的に解説します。
朝令暮改とは?その意味と背景
朝令暮改の定義と読み方
「朝令暮改(ちょうれいぼかい)」という言葉は、朝に出した命令が夕方には変わることから、物事が定まらない様子を表現する日本語の成句です。
この言葉の読み方は「ちょうれいぼかい」ですが、そのままの意味で使うときは「朝令暮改」とそのまま発音します。
朝令暮改の由来と歴史
この言葉は、古代中国の故事に由来します。
中国の戦国時代に、ある国の君主が部下に朝に命令した内容を、夕方には反故にするという、非常に不安定な指導をしていたことから生まれた言葉です。
このようなリーダーシップの問題が後に中国以外の国々にも影響を与え、特に日本では組織のリーダーが直面する「振れ幅」の大きい判断に対する警鐘として使われています。
朝三暮四との違い
「朝三暮四」とは、何度も変わることを表す成句ですが、「朝令暮改」とは微妙に異なります。
「朝三暮四」は、最初に言ったことが実際には変わらないことを意味しますが、朝令暮改は実際に指示が変わり、結果的にその場しのぎの対応をしていることが多いです。
朝令暮改な上司・社長の特徴と影響
言うことがコロコロ変わる人の心理
朝令暮改のリーダーは、物事を決める際にその場の状況に流されやすいという心理的特徴を持っています。
決定に至るまでの自信のなさや、判断を急いでしてしまうことが影響している場合もあります。
判断基準が不安定であるため、目の前の問題を解決しようとするあまり、結果としてその場しのぎの答えを出してしまうことが多いです。
上司や社長としての評価
上司や社長としての評価は、安定感と信頼感を大切にするため、朝令暮改な態度は非常にマイナスに働きます。
部下から見ても、何をしているのか分からない、または判断に一貫性がないと感じられることが多く、その結果、リーダーシップに対する信頼感が薄れてしまうことになります。
部下とのコミュニケーションへの影響
部下とのコミュニケーションにおいても、リーダーがコロコロと指示を変えると、部下は混乱し、何を信じて行動すべきかが不明確になります。
これは、業務の効率を下げる原因となり、組織全体の生産性にも悪影響を与えることになります。
経営方針の変化と社員の反応
経営方針が頻繁に変更されると、社員は次第に方針に対する適応力が低くなり、「また方針が変わったのか」と感じてしまいます。
結果として、社員のモチベーションや業務に対する意欲が低下し、組織全体の士気も下がってしまうことが考えられます。
朝令暮改のメリットとデメリット
メリット:臨機応変な対応の価値
朝令暮改には、臨機応変に状況に対応するというメリットも存在します。
急な市場の変動や社内の問題に直面した場合、指示を変更することで、組織が柔軟に対応できるという点です。
これにより、業務の進行を一時的に止めることなく、すぐに新しいアプローチを取ることができる場合もあります。
デメリット:社員の信頼の低下
しかし、朝令暮改を繰り返すことで、最も大きなデメリットは社員の信頼低下です。
リーダーがコロコロと方針を変更すると、社員はその言葉に価値を見いだせなくなり、リーダーとしての信頼が失われます。
最終的には、社員のパフォーマンスにも悪影響が出て、チーム全体の目標達成が難しくなることも考えられます。
職場の雰囲気への影響
頻繁な指示変更は、職場の雰囲気に深刻な影響を与えます。
社員間に不安感が広がり、業務が滞る原因となるだけでなく、コミュニケーションがギクシャクすることもあります。
また、指示が明確でないことで、部下がリーダーに対して不満を抱えるようになり、全体のチームワークが弱まってしまう危険もあります。
まとめ
朝令暮改なリーダーシップは、一見柔軟で臨機応変な対応として評価されることもありますが、実際には社員の信頼を失う原因となり、職場の雰囲気にも悪影響を与えます。
指示や方針がコロコロ変わることで、社員の混乱やモチベーション低下を招くため、リーダーとしては安定した判断力と明確な指示を求められることが重要です。
一方で、状況に応じて柔軟に対応することも必要であり、そのバランスを取ることが成功するリーダーシップのカギとなるでしょう。