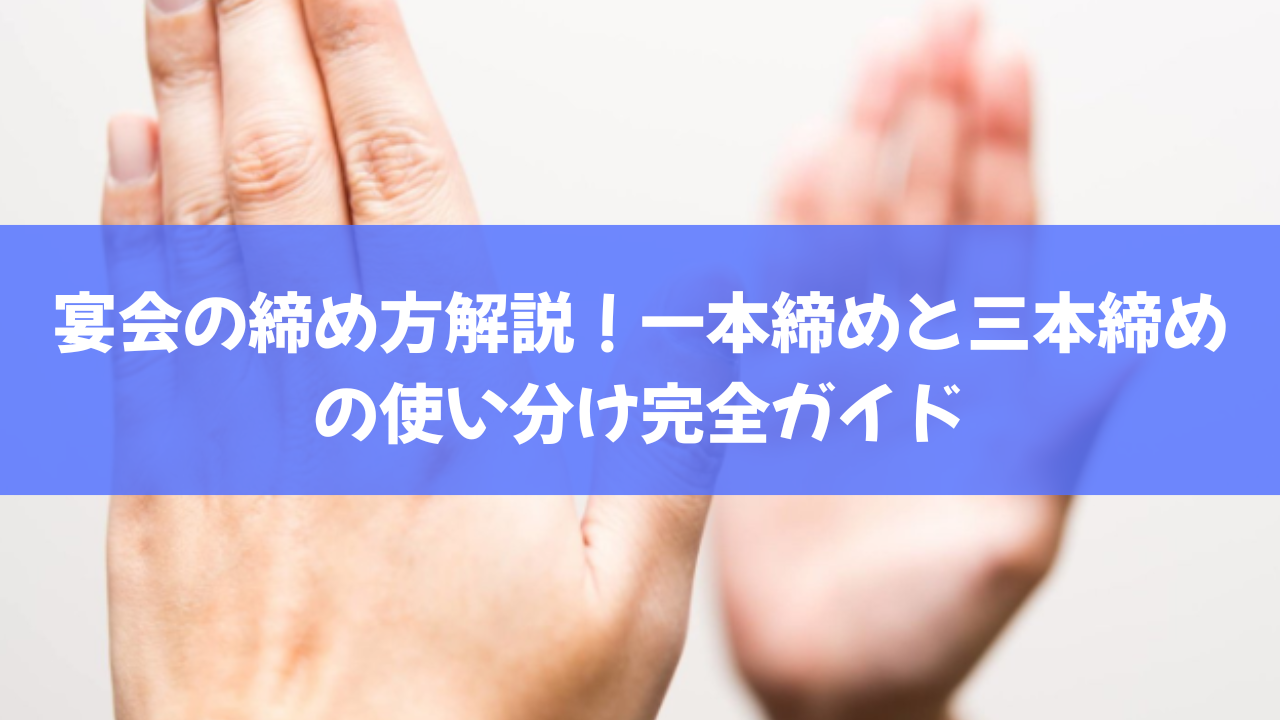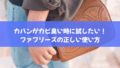宴会や仕事の打ち上げの最後に行う「締め」。その代表的なものが「一本締め」と「三本締め」です。何となく雰囲気で行っている方も多いですが、実はそれぞれに意味や使い分けのマナーがあります。この記事では、一本締めと三本締めの違いや正しいやり方、挨拶例文までをわかりやすく解説します。
宴会の締め方とは?

宴会の重要性とその役割
宴会は、日常の労をねぎらい、参加者同士の親睦を深める大切な場です。その締めとなる「一本締め」や「三本締め」は、宴会の終わりを明確にし、全員の気持ちを一つにまとめる重要な儀式といえます。単なる拍手ではなく、感謝と敬意を込めた「締めの文化」が日本には根付いています。
さらに、宴会の締めは単なる儀礼ではなく、その場を円満に終えるための“空気を整える仕上げ”のような役割も果たします。参加者が一体となって拍手を打つことで、会話やお酒の余韻を静かにまとめ、気持ちよく帰路につくきっかけとなります。
宴会の締め方の一般的な流れ
一般的な宴会では、幹事や上司が最後に挨拶をし、そのあとに「締め」が行われます。「それでは一本締めで締めたいと思います」などの合図で全員が心を合わせて手を打ちます。
会の流れをきれいにまとめるため、あらかじめ誰が締めを行うかを決めておくのがポイントです。また、会の内容や雰囲気に応じて「一本締め」「三本締め」「万歳三唱」などを使い分ける場合もあります。
正式な式典では司会者が進行をリードし、カジュアルな集まりでは幹事が率先してリズムを取るなど、柔軟に対応することが大切です。
一本締めと三本締めが使われる場面
一本締めは、会議や小規模な集まりなど「一区切り」に使われることが多く、三本締めは、会社の創立記念や大規模な式典など「完全な締め」に使われます。つまり、場の格式や規模によって使い分けるのが一般的です。
例えば、社内会議の後の懇親会では一本締め、取引先を交えた周年行事では三本締めといったように、相手への敬意やイベントの重みを考慮して選ぶことが重要です。
一本締めの意味と由来
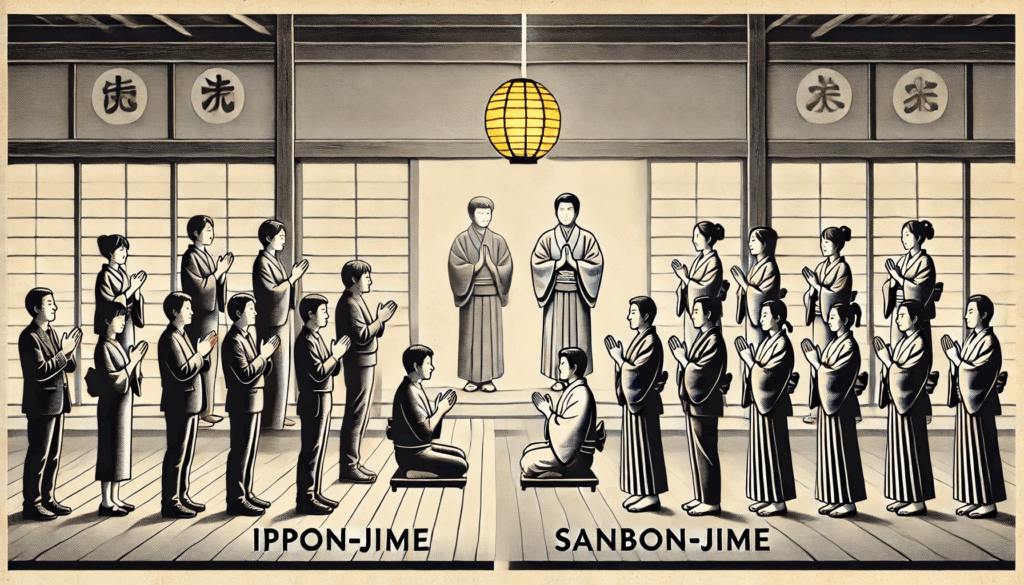
一本締めの由来
一本締めは、江戸時代の商人文化が発祥とされ、商売繁盛や成功を祝う「手締め(てじめ)」の一種です。元々は「三三七拍子」などの複数の手拍子の中から、より簡潔で実用的な形として生まれたといわれています。
手を打つことで心を清め、新しいスタートを切るという意味も含まれています。
一本締めのやり方
一本締めは、代表者の「お手を拝借!」という掛け声で始まり、「いよーっ、パン!」と1回だけ手を打ちます。この「パン!」には、区切りをつける意味と、参加者全員の気持ちをそろえる意味があります。
全員のタイミングがそろうことが最も重要です。これがうまく決まると、自然と一体感が生まれ、会場の雰囲気が心地よく締まります。
一本締めのメリット
短時間で全員の気持ちを一つにできるうえ、フォーマルにもカジュアルにも対応できる柔軟さが魅力です。また、静かに締めたい場面や時間が押しているときにも使いやすく、誰でも実施しやすいのが特徴です。
上司や主催者が一本締めを行うことで、場をスマートにまとめる印象を与えることができ、参加者への感謝の気持ちを自然に伝える手段にもなります。
三本締めの意味と由来

三本締めの由来
三本締めも江戸時代の商人文化に由来します。「祝い事をより盛大に締めくくる」という意味を持ち、一本締めを3回繰り返す形で構成されています。三という数字は古来より「めでたい数」とされ、成功・繁栄・感謝の象徴とされています。
三本締めは「団結」と「繁栄の継続」を象徴する締めとして現代でも多くの式典で用いられています。
三本締めのやり方
三本締めは、「お手を拝借!」の掛け声のあと、「いよーっ、パン!」を3セット行う形です。リズムが長くなる分、式典やパーティーなど格式の高い場面に適しています。
リズムを正確にそろえることが大切で、進行役が声を張ってテンポを作ると会場全体がまとまりやすくなります。
三本締めの利用シーン
三本締めは、企業の創立記念式典、結婚式の披露宴、町内会の行事など、正式なイベントの締めに最適です。大人数が集まる場では、三本締めによって一体感を共有する効果が生まれます。
一本締めと三本締めの違い

一本締めと三本締めの具体的な違い
一本締めは1回の拍手で区切りをつける「小締め」、三本締めは3回繰り返す「大締め」とされています。一本締めは簡潔でスピーディー、三本締めは華やかで正式な印象という違いがあります。
会の目的や雰囲気によって選び分けるのがスマートです。特に、完全終了の場面では三本締めが最適です。
一本締めと一丁締めの違い
「一丁締め」は、手を1回だけ打つ点では同じですが、「いよーっ」の掛け声を省略する略式スタイルです。気軽な場で使われることが多く、関西では特に一般的です。
地域ごとの使い分けの違い
関東では「一本締め=3・3・3・1の10拍子」、関西では「一丁締め=パン!1回」といったように、地域によって定義が異なることもあります。事前に確認しておくとスムーズです。
旅先や異業種交流会などでは、その場の主流に合わせて締め方を選ぶのがマナーです。
宴会での挨拶例文

一本締めの挨拶例文
「それでは、皆さまのおかげで本日の会も盛況のうちに終えることができました。今後のますますのご発展とご健康を祈念いたしまして、一本締めで締めたいと思います。お手を拝借! いよーっ、パン!」
感謝と前向きな気持ちを簡潔に伝えるのがポイントです。最後に「本日はありがとうございました」と添えるとより丁寧です。
三本締めの挨拶例文
「本日はお忙しい中ご参加いただき、誠にありがとうございました。皆さまのご活躍と今後のさらなる発展を祈念しまして、盛大に三本締めで締めさせていただきます。お手を拝借! いよーっ、パン!(×3)」
三本締めでは、感謝と未来への願いを込めた言葉を加えると締まりが増します。
まとめ
宴会の締め方には、場の雰囲気や目的に合わせた意味があります。一本締めは手軽に気持ちをまとめる小締め、三本締めは大きな節目を祝う大締めです。
正しいやり方と使い分けを知っておくことで、場の空気を引き締め、印象をより良くすることができます。次の宴会では、自信をもって締めを担当してみましょう!