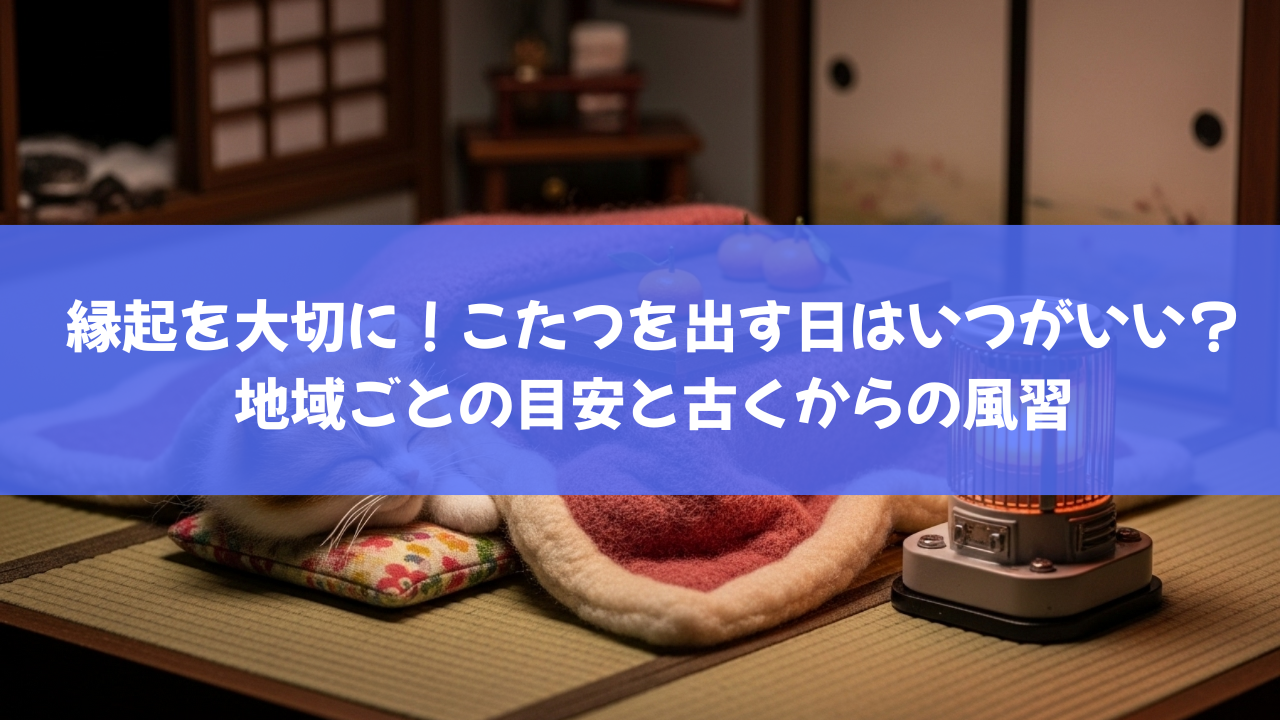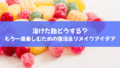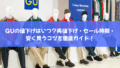肌寒さを感じ始めると、恋しくなるのが「こたつ」ですよね。
でも「こたつを出す日はいつがいいの?」「縁起の悪い日はあるの?」と気になる方も多いのではないでしょうか。
昔からこたつを出す時期には意味があり、「亥の日」に出すと火事を防ぐと言われています。
また、地域によって出す時期の目安も少しずつ異なります。
この記事では、縁起の良い日や地域ごとの出すタイミング、さらに出す前にチェックしておきたい準備や風水のポイントまで、やさしく解説します。
この記事を読めば、気持ちよく冬を迎える“こたつ開き”ができますよ。
こたつを出してはいけない日と縁起のいい日は?

こたつは「亥の月・亥の日」に出すのが縁起がいい
昔から「こたつ開き」は、亥の月(旧暦10月)・亥の日に行うと縁起が良いとされています。
これは、十二支の中で「亥」が火を防ぐ力を持つと信じられていたことからきています。
昔の暦では季節を「干支」で表しており、特に冬の始まりにあたる亥の月は“火の気を鎮める水のエネルギー”が強まるとされていました。
そのため、この時期に暖房器具を出すことで、一年を通して火の災いを避けられると信じられていたのです。
また、農作業を終えた時期でもあるため、家族が囲炉裏やこたつを囲んで団らんする始まりの日としても大切にされていました。
なぜ「亥の日」がいいの?火伏せの由来と無病息災の意味
「亥」は水の気を司るとされ、火事を防ぐ“火伏せ”の象徴です。
そのため、火を使うこたつや囲炉裏を出すのに最適な日とされてきました。
また、この日に始めることは家族の健康を守るとも言われています。
地方によっては「亥の日に新しい火を入れると家が安定する」との言い伝えもあり、火を扱う器具を使い始めることで“家の中心に温もりを迎える”という意味合いもありました。
現代では、火伏せの信仰に加えて「新しい季節を迎える節目の日」として大切にされており、冬の訪れを感じる行事として残っています。
出してはいけない日とされる時期(仏滅・土用・お彼岸など)
一方で、「仏滅」や「土用」などの期間を避ける地域もあります。
これは、古くから“新しいことを始めるには不向き”とされてきたためです。
特に仏滅は縁起が悪い日とされ、火を使う行為を避ける風習がありました。
また「土用」は季節の変わり目で体調を崩しやすい時期とも重なるため、無理をしないようにとの戒めでもありました。
ただし、現代ではそこまで気にしなくても大丈夫。
自分や家族が心地よく冬を迎えられるタイミングで出すのが一番です。
気持ちの区切りとして「この日からこたつを出そう」と決めることで、暮らしにリズムが生まれます。
地域や家庭によって異なる「こたつ出し」の風習
地方によっては「立冬の日」や「初霜の日」にこたつを出す習慣がある地域もあります。
例えば東北では初雪の前、関西では立冬頃、九州では12月に入ってからなど、気候の違いが反映されています。
家族の会話の中で「うちはこの日」と決めているご家庭も多く、それもまた素敵な日本の風習ですね。
近年では、祖父母世代から受け継いだこたつ出しの習慣を“家族の伝統”として大切にする家庭も増えています。
季節を感じながら準備する時間は、心を落ち着かせる大切なひとときです。
昔の人が縁起を重んじた理由と現代の受け継がれ方
昔は火事が多かったため、“火を使う日やタイミング”に特別な意味を持たせていました。
そのため、こたつを出す日を誤ると災いが起こるとまで信じる地域もありました。
今では安全な電気こたつが主流ですが、それでも「季節の節目を大切にする」「家族の健康を祈る」といった想いは変わりません。
こたつを出すという行為は、単なる家事ではなく、“一年の無事を願う小さな儀式”として現代に息づいています。
こたつと「亥の日」の関係を深掘り!歴史と文化を知ろう

平安時代から続く「火事除け」の習わし
「こたつ開き」は、平安時代の宮中行事がルーツとされています。
火を扱う季節に入る前に、安全を祈って儀式を行っていたのが始まりです。
さらに詳しく見ると、当時の貴族たちは冬を迎える前に火鉢や囲炉裏を整え、火の神に供え物をして家の無事を祈っていました。
この風習が庶民にも広がり、火を使う道具を出す日を特別に設けるようになったといわれています。
火を敬う文化が根づいていた時代だからこそ、「こたつ開き」には家族の安全と繁栄を願う深い意味が込められていたのです。
また、冬を迎える節目として、家の掃除や模様替えをするきっかけにもなっていました。
「亥」は火を鎮める干支?その象徴的意味
十二支の中で「亥」は“水のエネルギー”を持つ干支です。
そのため火の気を鎮め、家庭内の平穏を保つと考えられていました。
特に陰陽五行では「亥」は水の気が最も強まる時期とされ、乾燥しやすい冬の季節に火の事故を防ぐ意味を持ちます。
昔の人々は火を神聖なものとして扱い、同時に恐れてもいました。
そのため、火を鎮める象徴である亥の日を選んで火を使う準備をすることで、一年間の無事と繁栄を祈る風習が自然に生まれたのです。
現代においても、暦や干支を暮らしに取り入れることは、季節の流れを意識し、自然と調和して生きる知恵のひとつといえるでしょう。
京都・奈良・東北など、今も風習が残る地域例
京都や奈良などでは、今も“亥の子餅”を食べて火事除けを祈る風習が残っています。
東北でも「亥の日に火鉢やこたつを出す」といった文化が続いており、地域ごとに形を変えて受け継がれています。
さらに中国地方では「亥の子行事」と呼ばれる子どもたちの行列があり、竹筒を叩いて「火の用心」を呼びかけながら餅を配るなど、地域ならではのスタイルで伝承されています。
また、九州では“亥の子餅”に黒豆や小豆を混ぜて作り、無病息災を願うなど、食文化と結びついているのも特徴です。
これらの風習は単なる迷信ではなく、火災の多かった時代に人々が生活の中で築いた“知恵のかたち”。
現代の私たちも、そうした文化を感じながらこたつを出すことで、心に小さな季節の儀式を持つことができます。
こたつを出す時期の目安は?地域による違いをチェック

北海道:初雪前の10月中旬〜下旬
北海道では早いところで10月半ばからこたつを出す家庭が多いです。
雪が降る前に暖房器具を準備しておくのが基本です。
広い地域のため、道北や道東では早ければ9月末から寒さが厳しくなることもあり、こたつだけでなくストーブとの併用が一般的です。
室内でも冷え込みが強いため、断熱マットや厚手のラグを合わせて使うなど、冬の暮らしの工夫が欠かせません。
東北地方:11月上旬〜立冬前後
立冬(11月上旬)を目安に出す地域が多く、昼夜の寒暖差が激しくなる時期に合わせて準備します。
朝晩の冷え込みが一気に進むため、家族全員で「そろそろこたつ出そうか」と話題になる季節です。
雪が降り始める前に出しておくことで、慌てず快適に冬を迎えられます。
特に日本海側は風が強く、冷たい空気が入りやすいため、部屋全体を温める前にこたつを活用するご家庭も多いです。
北陸地方:11月中旬〜寒波が来る前
湿度が高く冷え込みやすい北陸では、早めの冬支度が基本。
寒波が到来する前にこたつを出すのが安心です。
雪が多く積もる地域では、こたつが家族の中心になることも。
外出が減る季節に備え、冬用ラグや厚掛け布団を新調する家庭もあります。
また、天気が変わりやすい北陸では、晴れた日にこたつ布団を干しておくと快適に過ごせます。
関東地方:11月下旬〜12月初旬
晴れの日が多く比較的暖かいですが、朝晩の冷え込みが増える頃が目安です。
マンションでは比較的遅めの11月下旬に出す家庭が多く、一軒家では11月中旬から準備を始める方もいます。
秋の終わりに紅葉を楽しんだあと、冬支度としてこたつを出すという流れが一般的です。
また、都市部ではデザイン性の高い「リビングこたつ」も人気で、インテリアの一部として取り入れられています。
関西地方:11月中旬〜下旬
京都や奈良など内陸部では冷え込みが早く、下旬にはこたつが登場します。
盆地特有の寒さで朝晩の温度差が大きく、底冷えを感じやすいため、早めに準備する家庭も多いです。
一方で大阪や兵庫など海沿いの地域は比較的温暖で、12月に入ってから出すケースもあります。
関西では昔から「お歳暮の準備を始めたらこたつを出す」といわれるほど、冬支度の目安とされてきました。
九州地方:12月初旬〜冬本番前
日中は暖かくても朝晩の冷えが強まる12月上旬が目安です。
南部の鹿児島や宮崎では、気温が20℃を超える日もあるため、こたつを出す時期が遅めになる傾向があります。
寒暖差があるため、電気毛布やホットカーペットと併用して“段階的な冬支度”をするのが九州流。
冬の訪れを感じる12月中旬頃には、家族団らんの場としてこたつが欠かせません。
沖縄:こたつ文化が少ない?代わりの暖房事情
暖かい沖縄ではこたつ文化は少なめ。
代わりに電気カーペットやブランケットを使う方が多いです。
とはいえ、冬場の朝晩は20℃を下回ることもあり、最近では省エネタイプの小型こたつや足元ヒーターを取り入れる家庭も増えています。
湿気が多い気候のため、断熱よりも除湿と保温を意識した使い方がポイントです。
また、沖縄ならではの“こたつ代わり”として、カラフルなブランケットや南国柄の布団を使って楽しむスタイルも人気です。
こたつを出す前にやっておきたい準備チェックリスト

こたつ布団の洗濯・クリーニングのタイミング
収納していた布団にはホコリやダニがついていることも。
天日干しや洗濯をして清潔に整えましょう。
さらに、素材によってはクリーニング店に出すのも安心です。
長期間しまっていた場合は、軽く叩いてホコリを落としてから洗濯ネットに入れ、優しく洗うのがポイントです。
日光に当てることで殺菌効果もあり、ふんわりとした肌触りが戻ります。
晴れた日に2〜3時間ほど干し、完全に乾かすとカビの発生を防げます。
こたつ布団カバーを新調する場合は、色味や素材を季節に合わせて選ぶとインテリアの雰囲気も明るくなります。
ヒーター・コードの劣化確認と安全対策
コードの折れや焦げがないかチェック。
古いものは交換し、火災防止につなげましょう。
特に差し込み口の金属部分にサビや黒ずみがある場合は要注意。
通電部分が緩んでいると発火の原因になります。
また、コンセントまわりのホコリを定期的に拭き取り、延長コードのたこ足配線を避けることも大切です。
こたつヒーター部分は掃除機でホコリを吸い取り、内部が詰まらないようにメンテナンスを行いましょう。
心配な場合はメーカーのサポートセンターで安全点検を受けるのもおすすめです。
床やカーペットの掃除・ダニ対策
こたつの下にホコリがたまりやすいので、掃除機をかけて清潔に。
防ダニマットを敷くのもおすすめです。
さらに、重曹スプレーや天然アロマを使って除菌・消臭をすると気持ちよく冬を迎えられます。
床の汚れは放置すると湿気やカビの原因になるため、こたつを設置する前にしっかりと乾拭きをしておきましょう。
カーペットを敷く場合は、防炎加工・抗菌仕様のものを選ぶと安心です。
ペットや小さなお子さんがいる家庭では、洗えるカーペットを選ぶとお手入れがぐっと楽になります。
節電モード・安全スイッチの確認ポイント
節電モード付きのこたつは、消費電力を抑えて快適さを保てます。
安全スイッチが正しく作動するかも忘れず確認を。
また、温度設定を低めにしてひざ掛けなどを併用すると、体感温度が上がりやすく省エネになります。
最近では人感センサー付きこたつや、自動オフ機能がついたモデルもあり、寝落ちしてしまっても安心です。
電気代が気になる方は、断熱シートを床下に敷いて熱を逃がさない工夫をするのもおすすめ。
細かな準備をしておくことで、冬の間ずっと安心・快適にこたつを楽しめます。
風水的に見る!こたつの置き場所と運気アップ術

金運・健康運がアップすると言われる方角
こたつを南東(健康運)や北西(金運)の方角に置くと、良いエネルギーが入るとされています。
風水では南東は“木”の気を持ち、成長や人間関係を育む方位。
こたつをこの位置に置くと、家庭内のコミュニケーションが円滑になり、心も体も健やかに過ごせるといわれています。
北西は“金”の気を持つため、仕事運や金運を引き寄せるのにぴったり。
特に家の中心から見て北西の位置にこたつを配置すると、安定感と豊かさが高まるとされています。
家の間取りに合わせて、こたつの向きや座る位置も意識するとより効果的ですよ。
避けたほうがいい配置(玄関・ドア近くなど)
出入り口付近や風の通り道は気が乱れやすい場所。
温かい気が逃げない位置に置くのが◎。
また、玄関やトイレの近くなど“外気が入りやすいエリア”は、風水的にエネルギーの流れが不安定になりやすいとされています。
こたつを落ち着いて使うためには、壁際や部屋の中央など、家族が自然と集まりやすい位置がおすすめです。
さらに、床下に断熱マットを敷くことで温かい空気を逃がさず、風水的にも“安定した気”を保つ効果があります。
可能であれば観葉植物や天然素材のインテリアを近くに置くと、気の流れがより穏やかになり、心地よい空間を作れます。
暖色系のこたつ布団がもたらす心理的効果
オレンジやベージュの布団は安心感を与え、家族の団らん運を高めるといわれています。
さらに、風水の色の力を意識して選ぶのもポイントです。
赤やオレンジは“陽の気”を持ち、元気や活力を与える色。
ベージュやアイボリーは“土の気”を象徴し、家庭運を安定させるといわれます。
寒色系のブルーやグレーを取り入れる場合は、アクセントカラーとして小物に使う程度にすると◎。
照明も重要で、暖色系の柔らかな光を合わせることでリラックス効果が高まり、家族の会話が自然と増える空間になります。
冬のインテリアに少し風水を取り入れるだけで、心も温まる“幸運こたつ空間”が完成します。
こたつを出すのにおすすめの吉日カレンダー

立冬(りっとう):冬支度の始まりに最適
暦の上で冬の始まりを意味する日。
季節の変わり目に合わせてこたつを出すのにぴったりです。
立冬の日にこたつを出すことで、「冬を迎える準備が整った」という節目を感じることができ、気持ちも新たに年末の忙しさに備えることができます。
古くから立冬は農作業を終え、冬の備えを始める日として大切にされてきました。
現代でも「冬支度の日」として掃除や模様替えをする家庭が多く、こたつ出しをこの日に合わせるのは理にかなっています。
家族で温かいお茶を飲みながら布団をセットすれば、冬の訪れを実感できる素敵な時間になります。
亥の日:火伏せ・家内安全の象徴
火を鎮め、家を守る日とされてきた“亥の日”は、古くから多くの家庭で「こたつ開き」に選ばれてきました。
亥は十二支の中で「水の気」を司り、火災や病気を遠ざけるといわれています。
この日にこたつを出すことで、火のトラブルを避け、家族が健やかに冬を過ごせると信じられてきました。
地域によっては、亥の日に“亥の子餅”を食べたり、火の神にお供えをするなど、さまざまな風習が残っています。
現代では、実用的な意味だけでなく「季節の始まりを大切にする心」を育む日として、SNSなどでも「#亥の日こたつ開き」として注目を集めています。
天赦日・一粒万倍日:新しいものを出すのに縁起の良い日
こたつを新調したり、こたつ布団を新しくするなら吉日を選ぶのもおすすめです。
天赦日は“天がすべての罪を赦す日”といわれ、日本の暦の中でも最上級の吉日。
一粒万倍日は“努力や始めたことが何倍にもなって返ってくる”という意味があり、何かを始めるのに最適な日とされています。
この2つが重なる日は特に縁起が良く、新しい家具を購入したり模様替えをするのにもぴったりです。
こたつ布団を新調する際には、温かみのある色を選ぶことで運気アップにもつながります。
大切なのは、カレンダーの縁起を取り入れながら、自分や家族にとって「心地よいタイミング」を選ぶこと。
暦に寄り添う暮らしは、自然の流れを感じながら穏やかに季節を過ごすきっかけになります。
まとめ:昔の知恵を取り入れて、自分らしい冬支度を
こたつを出すタイミングには、昔ながらの知恵と想いが詰まっています。
亥の日や立冬などの縁起の良い日に出すことで、冬の始まりを気持ちよく迎えることができます。
また、地域の気候や家族のライフスタイルに合わせて、無理のないタイミングで準備するのが大切です。
風水や暦を取り入れつつ、安全で温かい“自分らしい冬支度”を楽しんでくださいね。